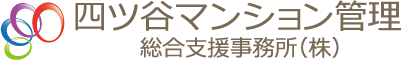概要
日本では一般的な管理方式である「理事会方式」は、昭和57年の中高層共同住宅標準管理規約がこの方式を採用したことに始まります。
区分所有者の中から役員を選出し、理事会を構成。理事長を管理者とし、理事会が業務執行する。理事長及び理事への負担は大きいものの、「区分所有者の区分所有者による区分所有者のための」運営が行われるため、民主的で主体的な運営が行われます。
現在、この管理方式に、あらたな波が押し寄せてきているとも言われています。役員を外部から起用、あるいは管理会社を管理者とする手法です。しかし、理事会方式が問題なく行われている管理組合に、むりやり外部管理者を投入する必要などありません。
日本においては、理事会方式が浸透しているといってよく、ノウハウもある程度確立されています。外部管理者方式に踏み切るのは、最後の手段といって良いでしょう。
一般的な管理組合は「権利能力なき社団」にあたります。権利能力なき社団は、自然人や法人が持つ権利能力を持たないことから、権利の主体となり得ません。そのため、特に以下の3つの場面において、注意が必要となります。①契約時…管理組合名で契約することはできず、理事長(管理者)のその肩書と氏名において契約を締結します。②登記時…管理組合名で登記することはできず、組合員全員の連名で登記します。これに対し、③訴訟提起時…民事訴訟法29条の規定により、法人でない社団に当事者能力*が認められます。区分所有法26条5項より、理事長(管理者)が原告又は被告となり得ると解されています。ただし、規約の定めまたは総会の決議が必要となります。※当事者能力→民事訴訟の当事者となることができる一般的な資格
理事会運営
理事会の形態・活動内容は、マンションの数だけあるものと思いますが、理事長が毎年一回総会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)ということは共通です。
そのため、理事会は前年度総会で承認された活動計画の執行について会計年度終了後の総会に報告(議案上程を含む)すべく一年を進めていきます。
大きな事業を背負っている場合、あらかじめ計画して進めないと一年はアッという間に過ぎ去ってしまいます。首尾よく業者を理事会に招聘したり、住民へのアンケート取得・説明会の開催なども必要となります。
また、理事会は、漏水対応、マンション内で事故等の対応など、即時の対応も求められます。そのさいに、区分所有法や管理規約の考え方に関する知識不足から事例に適切に対処できないことが考えられます。
弊社では、マンションの理事会に顧問として出席し、適宜アドバイスを行います。
弊社のサービス内容
理事会顧問業務
- 業務内容
-
- 事案に関するアドバイス
- 業者見積書の確認
- 導入効果
-
- 理事長、担当理事の負担軽減
- 導入手順
-
- 理事会決議
- 総会決議
費用
(単体の場合)月額 40,000円(税込)~
※マンションの規模に応じて変動いたします。
管理会社との協働・牽制
2000年にマンション管理適正化法が制定され、「マンション管理士」という国家資格が創設されました。その目的は、管理組合が知識不足などにより、管理について管理会社に依存せざるを得ないところ、管理組合の立場に立って相談を受ける専門家を置くというものでした。当時のマンション管理会社は金銭事故を起こしたり、暴利をむさぼるなど、その立場を利用した粗野な行為が散見されたようです。
制定から24年が経ち、マンション管理業界全体を牽引するような管理会社が現れたり、管理会社の団体において、「マンション管理適正評価制度」が草案されるなど、様相は変化しました。
しかし、いまだ、一部の管理会社においては、例えば賃貸化・空室化等の問題に対応できず、住民からの要望、問題提起を無視し続けるといったところもあるようです。
弊社では、管理会社と協働しつつも、同時に牽制しながら、管理組合でおこる問題について、解決をはかるべく行動します。
未収金の回収
管理組合の平穏を脅かすもの、それが未収金です。1回程度の未収であれば、仕方がありませんが、2度3度となるとことは重大です。
未収金は、徒過すると、払えるものまで払えなくしてしまう危険があるため、早急な対応が必要です。
標準管理規約 別添3では、以下のような対応ひな形を用意しています。
滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート
(標準管理規約 別添3(抜粋))
(1)督促
| <督促手順の例> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 電話、書面(未納のお知らせ文)による連絡 | |||
| 2ヶ月目 | 電話、書面(請求書)による確認 | |||
| 3ヶ月目 | 電話、書面(催告書) | |||
| 4ヶ月目 | 電話、書面、自宅訪問 | |||
| 5ヶ月目 | 電話、書面(内容証明郵便(配達記録付)で督促) | |||
(2)滞納者の保有財産の調査」
- 滞納者の専有部分等の抵当権の有無等及び専有部分等以外の資産の有無について調査を行う(現住所とその直前に居住していた市区町村及び勤務先市区町村)。
- 金融機関の調査は、区分所有者にあらかじめ同意を取る必要がある。
- 課税当局(地方自治体)の固定資産台帳については、本人の同意書を携えて調査する。
- 登記情報については、地番や家屋番号等が分かれば情報の取得が可能。
(3)区分所有法第7条の先取特権の実行
- 滞納管理費等に係る債権は、区分所有法第7条の先取特権の被担保債権となっているため、債務名義(確定判決等)を取得せずとも、先取特権に実行としての担保不動産競売を申し立てることが可能。これにより、一般債権者に優先して弁済を受けることができる。
- 区分所有法第7条の先取特権は、公租公課及び抵当権等の登記された担保権に劣後する。
- したがって、先取特権の実行による滞納管理費等の回収は、抵当権が担保する融資残額などを控除しても、当該マンションの売却代金から滞納管理費等の回収が見込まれる場合には実行性のあるものとなる。買受可能価額がそれらの優先再建等の見込額に満たない場合、担保不動産競売手続きは、取り消される(無剰余取消し)
(4)区分所有者の資産に対する強制執行
- 滞納者の預金その他の保有財産の存在が判明した場合には、これに対する強制執行により滞納管理費等の回収を図ることが考えられる。強制執行の場合は、まず確定判決等の債務名義を取得することが必要である。しかし、管理組合は、債務名義を取得しただけで直ちに滞納管理費等を回収できるわけではなく、裁判所に対し、滞納者の財産に対する強制執行(不動産執行、動産執行、債券執行など)を申し立てる必要がある。
- 強制執行は、滞納者の保有財産がどこにあるか十分調査してから行うべきである。手続き費用などに比して十分に回収できない等の問題があるからである。
(5)区分所有法第59条による区分所有権の競売請求
- 区分所有法第59条の不動産競売において、滞納管理費等の債権に優先する債権があって、「剰余」を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続きをすることができるとした裁判例があり(東京高決平成16年5月20日(判タ1210号170頁))、区分所有者がいわゆるオーバーローン状態でも競売手続きを実施することができる可能性がある。この場合には、区分所有法第8条により特定承継人である競落人に滞納管理費等の支払いを求めることができる。ただし、買受可能価額が競売の手続き費用を下回るような場合には、無剰余取消しとなる可能性があることも考慮する必要がある。
(公財)マンション管理センター 「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(最終改正)令和3年6月 pp94-96
プライバシーに関し誰もが慎重になった昨今、滞納があるとはいえ、自宅を直接訪問するとは前時代的すぎると考える人もいるかもしれません。訪問する側の理事長・役員にとっても非常に気が重い話しですし、何かのことで逆恨みされても困ります。そのため、管理組合によっては、滞納解消のための自宅訪問は行わないとするところがあるようです。しかし、経験上(で恐縮ですが)、上手くいけば、即滞納解消につながる可能性があるのもこの役員の訪問(面談)です。過去に支払督促や少額訴訟などの手続きを経験し、非常に面倒と感じた理事会の中には、早いうちから自宅訪問(面談)を試すことがあるように思います。さて、その際に、気をつけるべきことですが、相手の話をよく聞くということでしょう。せっかく設けた機会ですから、相手と一緒に解決策を探るくらいの時間的余裕と心構えで訪問しては如何でしょうか。その結果、管理組合が今後留意すべき事項について知ることができるかもしれません。しかし、他方において、あくまでも規約に沿った対応をすることも忘れてはなりません。この点を逸脱すると、以後の管理組合運営に影響を及ぼすことになりかねませんので、注意が必要です。
役員のなり手不足
役員の成り手不足に対し、決定打といえるものはありませんが、下記方法により遣り繰りすることになります。
役員の成り手不足の対応策
| 1. | 規約改正による役員資格の見直し | 組合員だけではなく、配偶者や同居する一親等の成人親族も可能とする 理事の代理出席を可能とする。 | |||||||||
| 2. | 役員報酬の支払い | 役員に報酬を支払い、理事会の活性化に繋げる。 | |||||||||
| 3. | 運営協力金の徴収 | 輪番制の役員の辞退者及び外部居住組合員に運営協力(金銭)を求める。 | |||||||||
| 4. | 任期の長期化 | 役員の任期を2~3年に規定する。 | |||||||||
| 5. | 専門家の活用(顧問契約等) | マンション管理士などの専門家に依頼し、理事会・総会等の開催支援を受ける。 | |||||||||
| 6. | 外部管理者の起用 | 外部者に役員を依頼する。(別途契約による) | |||||||||
弊社のサービス内容
管理組合の状況に応じて、有効な対応策を提案し、対応を支援いたします。また、5.専門家としての顧問業務、6.外部管理者業務についても承ります。
役員のなり手不足対応
- 業務内容
-
- 事案に関するアドバイス
- 導入効果
-
- 理事会の継続性の改善
- 導入手順
-
- 理事会決議
- 総会決議
費用
理事会顧問業務/月額 40,000円(税込)~
外部役員就任/月額 55,000円(税込)~
※マンションの規模に応じて変動いたします。
理事会の役員の選任にあたり、輪番制を敷いている管理組合も多いことと思います。輪番制は、組合員が組合員としての権利と義務を平等に果たすという意味において、とても理想的な手法です。
しかし、この輪番制を敷いている管理組合が上手く運営できているかというと必ずしもそうとも言い難い部分があります。輪番制において、毎年滞りなく理事会運営していくには、優秀な管理会社担当者や、マンション管理士の力が必要となります。
管理組合が自ずからいかにうまく運営していくかを考えると、個人的には、何人かのリーダー達が長期に渡って管理組合運営に携わることは、良策であるように思います。
権力は持った時から腐敗を始める、ともいいますので注意は必要ですが、賢明で熱心な複数のリーダー達を持つことは、その管理組合に幸をもたらす可能性があります。もし、管理組合にそういう人々が存在したら、輪番制のみにこだわることはないかもしれません。
リーダー達によって道が開かれ、気運が高まり、組合員の関心がマンションに注がれるようになれば、しめたものです。「私たちのマンションという意識」や、「マンションに対する誇り」が生まれてくるかもしれません。
もちろん、規約や法律を顧みず、自分の経験則のみで判断するようなリーダーは、歓迎できませんが。
共用部保険の付保
管理組合にとってマンション共用部保険の加入は必須です。そのため、標準管理規約単棟型24条1項では、管理組合の保険会社との契約締結につき総会の決議によらず規約による包括的な承認について規定してます。実際上は、地震保険・個人賠償包括等の付保及び解約については、念のために総会決議とすることが考えられますが、規約上は不要です。